こんにちは!元音楽の先生、みきちです☺
今回のテーマは、鍵盤ハーモニカで最初に教えたいこと【第2時編】です!
さて、第2回となる今回は、曲を演奏するために必要な
- 唄口(ホース)の持ち方
- 指番号
- 「ド」の位置
を習得させる、簡単で楽しい指導方法をご提案します。
💭指番号や「ド」の位置、楽しく分かりやすく教える方法が知りたい!
💭基礎がなかなか定着しない…
こんなお悩みをお持ちの先生、ぜひ参考にしてみてくださいね。
※ 本記事は前回の続きです! ※
計3時の授業を通して、鍵盤ハーモニカとの出会い~基礎の習得をスムーズに指導しよう!
というシリーズの2個目の記事です。
前回の記事通りに進めている前提で、授業の流れを提案します。
第1時~3時の大まかな流れと初回授業の流れについては
別の記事でご紹介しています。まだの方は先にこちらをご覧ください。
▼▽▼
💡この記事で分かること💡
☑ 鍵盤ハーモニカの「指番号」「『ド』の位置」「唄口(ホース)の持ち方」の指導方法
☑ 子どもたちが飽きずに楽しく基礎を習得できる方法
☑ 授業をスムーズに進めるための「合図」の作り方
授業の概要
本格的な曲の練習に入る前に、正しいフォームや奏法を楽しく体に染み込ませるのがねらいです。
✨授業後の理想の児童の姿
・指番号や「ド」の場所などの基本が自然に身に付いている。
・正しい持ち方や指使いを意識して、音を出すことを楽しめる。
⌛時数
全3時(本時は第2時)
🎹必要な道具
鍵盤ハーモニカ、メトロノーム
うたぐちのもちかた、ゆびばんごう、「ド」のばしょ をおぼえよう
❁めあて
うたぐちのもちかた、ゆびばんごう、「ド」のばしょ をおぼえよう
❁評価の観点(例)
思いに合った表現をするために必要な,範奏を聴いたり,リズム譜などを見たりして演奏する技能を身に付けている。(技)
❁大まかな本時の流れ
- 鍵盤ハーモニカを準備する
- 今日のめあての確認
- 唄口(ホース)の持ち方を知る
- 指番号を知る
- 「ド」の場所を知る
- 指と声で練習 ~まねっこリズム~
- 音出しアリで「まねっこリズム」
- 片付け・振り返り
- 時間があれば、「やさしいひつじ」を音名で歌う(次回の予習)
①鍵盤ハーモニカを準備する
『鍵盤準備』の合図で、鍵盤ハーモニカを演奏できる状態にします。
- ケースを開ける
- ホースを取り付ける
- 唄口が下に付かないようにセットする

準備ができたら、お隣さんと「ホースはしっかり付いてる?」「唄口は大丈夫?」と確認してみよう!
②今日のめあての確認

鍵盤ハーモニカにはいくつかのコツがあります。
今日は、上手になるための「合言葉」を3つ覚えるよ!
私は鍵盤ハーモニカの演奏のコツ(基礎・基本)は5つあると考えています。
それを「鍵盤ハーモニカの合言葉」としてまとめて繰り返し指導するのがオススメ!
「合言葉」の5つの内容は、
1.指番号
2.ドの場所
3.右手の形
4.タンギング
5.唄口の持ち方
リズムに乗って先生と子どもたちが呪文のように掛け合いをすることで、楽しく簡単に覚えられる仕組みです。
え、なんか怪しい宗教みたい…と思うことなかれ!習慣化すれば教師も楽だし児童も基本が定着しますよ!💪🏻💪🏻
詳しい内容や印刷するだけの一覧ポスターは、こちらの記事からどうぞ。
▼▽▼

今日は1番、2番、5番の3つをマスターしよう!
③唄口(ホース)の持ち方を知る
唄口の合言葉
先生:「左手」
児童:「OK!👌🏻」
先生:「真ん中持って」
児童:「まきつけて」
先生:「軽ーくはさんでドードードー はい!」
児童:(演奏)

まずは5番目の合言葉、「唄口の持ち方」からやってみよう!まずは見ててね。
「左手」って言われたら、みんなは「OK!」と返してください。OKマーク👌🏻を作るよ。
口を付けるところを唄口って言うんだけど、唄口の真ん中に印があります。
「真ん中持って」って言われたら、みんなは唄口の真ん中あたりを2本指で持って、「まきつけて」って言います。残りの指で優しく包む感じね。
次はみんなも一緒にやってみよう!
唄口は先っぽを唇で軽くはさむようにくわえるのが正しい演奏の仕方です。
「歯でガリガリ噛んだら、唄口が傷ついちゃう!だから挟むだけだよ」と、優しくくわえることを伝えましょう。
ここまでができるようになったら、一度、ホースを「鍵盤準備」の状態(唄口を演奏しない時の位置に戻し、垂れないようにセットする)に戻させます。
💡POINT💡
簡単で分かりやすい指示をするために、合図を作りましょう!
今後の学習がとってもスムーズになります💮
本記事では以下の2つの合図を使っています。
・「鍵盤準備」→鍵盤ハーモニカにホースがセットしてあり、話を聞くときの状態。
・「演奏用意」→唄口をくわえ、すぐに演奏を始められる状態。
もちろん言葉はこの通りである必要はありません。かけっこの時のように、「いちについて」「ようい」としてもいいですね。
指揮のようなハンドサインで唄口を準備するなど、言葉を介さない方法もあります。💬
唄口の持ち方に加え、『演奏用意』と『鍵盤準備』の合図を聴き分ける練習をしましょう。
雑談が得意な先生なら、雑談中に『演奏用意!』『鍵盤準備!』と合図を出して、反応できるか試してみても面白いですよ。😂
④指番号を知る
指番号の合言葉
先生:「指番号!」
児童:「いいね!は1番、2,3,4,5!」

鍵盤ハーモニカの演奏では、指に番号が付いているの。
合言葉は、「いいね!👍🏻は1番、2,3,4,5」だよ。一緒に言ってみよう!
いいね!でグッドサイン(サムズアップ👍🏻)。順に指を上げます。
定着させるために、こんなクイズもおすすめです。

先生が左手をパーにして、子どもたちに向けます。
右手にペンなどを持ち、左手の指を一本ずつ指して「これは何番?」と聞いていきましょう。
だんだんスピードアップすると盛り上がりますよ🔥
⑤「ド」の場所を知る
「ド」の場所の合言葉
先生:「ドー」はどこだ!
児童:「チョキ✌🏻で 押さえて ドレミファソ」(1,2,3,4,5の指で順に押さえていく。)
必ず先生の手元を見せながら、言葉と実演で丁寧に説明しましょう。
(鍵盤ハーモニカの実物だと小さくて見にくい場合は、鍵盤のイラストを拡大印刷しておくと便利です。↓良かったらそのまま印刷して使ってください😂↓)


車のクラクションの音、覚えてるかな?
(鍵盤を指さしながら)「2つのお山」を同時に押さえるんだったね。
右手を出して、真似してね。
グー✊🏻、チョキ✌🏻、パー🖐🏻!
パー🖐🏻に勝つのは~?
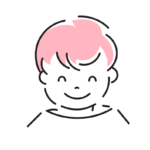
チョキ✌🏻!

そうです!じゃあ、チョキは何番と何番の指?

えーと、2と3!

その通り!2と3の指で、「2つのお山」を押さえてみよう。
指はそのまま、離さないでね。できた人は前を向きます。
(手元を見せながら)「2つのお山」のすぐ左側にある白い鍵盤が「ド」です。1の指で押さえます。
みんなもやってみよう!どうぞ。
このような流れで「ド」の場所を指導します。
場所が理解できたら、「ドの場所の合言葉」→「唄口の持ち方の合言葉」の順で、リズムに乗って実際に「ド」を演奏してみましょう!🎶
⑥指と声で練習 ~まねっこリズム~
ここからは基本をしっかり身に付けるための基礎練習を、ゲーム感覚で学習していきます!
実は…
鍵盤ハーモニカって、実はキーボードより難しいんです…!🤯
なぜなら、鍵盤ハーモニカは、指と口で違うことをするからです。
じゃあどうするか!
簡単です。慣れれば良いのです!笑
でも回数こなすのって大変!
こんな時は、簡単で楽しい、リズム模倣を使いましょう!
私はリズム模倣を「まねっこリズム」と呼んでいるのですが、例えば、先生が「ドードードー」と言ったら、子どもたちは真似をして「ドードードー」と返します。
活動としてはたったこれだけですが、組み合わせ次第でバリエーションが生まれます。
指の動きと口の動きを分けて、段階的に慣らしていきましょう。
✋🏻指の動き:前を向き、空中で指を動かす「空中指」と、鍵盤を使い実際に押して練習する「鍵盤指」
👄口の動き:音名を声に出す(ドレミ)と、息の出し方を練習する(トゥー)
練習ステップ(各30秒~1分で充分!)
- 空中指 と「ド」と声に出す
- 鍵盤指 と「ド」と声に出す
- 鍵盤指 と「トゥー」と息を出す(まだ音は出さない)
💡POINT💡
メトロノームを付けて行いましょう。4分音符=70~80くらいのテンポがおすすめです。オルガンの機能を使ってもOKですし、ググっても出てきます!
⑦音出しアリで「まねっこリズム」

みんな頑張ったから慣れてきたね!すごい!
じゃあ音を出してまねっこリズムしてみよう!
『演奏用意』って言われたら何するか、覚えてる?
まずは『演奏用意』で唄口の正しい持ち方ができているかチェック!
みんなができていることを確認したら、いよいよ音を出してまねっこリズムに挑戦です!
レベル2と題して、オクターブ上の「ド」も使って「高いド」「低いド」でまねっこリズムをしてみるのも面白いですね。
💡POINT💡
- 同じ音が連続する時は、「指は押したまま、息(舌)で区切るんだよ」と指導します。
- 児童が演奏する時は、手で舌の動きを表現してあげましょう。🤌🏻
手を舌に見立て、息を出す時🔊は、手首を使って「どうぞ」の動きをするように手を前に押し出します。息を止める時🔇は、反対に「おいで」の動作のように手前に動かします。 - 難しいリズムをする必要はありません。「たん うん たん うん」「たた たん たん」「たーーー(全音符)」など、簡単なリズムでOK!
ちなみに、まねっこリズムについて詳しく知りたい!という方、詳細や指導方法はこちらの記事からどうぞ。
⑧片付け・振り返り
『鍵盤片付け』の合図でお手入れ・片付けをします。
片付けが終わった人から、今日のめあてについて振り返りをしましょう。紙やタブレットで提出させてもOKですし、口頭で挙手させてもOKです。🙋🏻♀️
個人的には器楽は1人1人見てあげられる時間が少ないので、記録が残る方法がオススメです📝
もし時間が余ったら、次回「やさしいひつじ」(メリーさんのひつじ簡単バージョン)を歌うことを予告し、少し歌ってみても良いでしょう。「やさしいひつじ」の楽譜はこんな感じです。

まとめ
鍵盤ハーモニカ指導の第2回として、演奏の基本となる3つの「合言葉」を習得する授業アイディアをご紹介しました。
一つ一つの技術を、段階的に、楽しく、できる実感を持たせながら、身につけさせていくことが大切です。
ぜひ、児童の実態に合わせて試してみてくださいね。
次回は、いよいよ残りの「合言葉」をマスターし、簡単な曲の演奏にチャレンジします!
また覗いてみてくださいね。👀
音楽分からん!アイディアがない!相談できる人がいない!時間もない!
ほんの少しでも、そんな先生方のお力になれますように🎹✨





