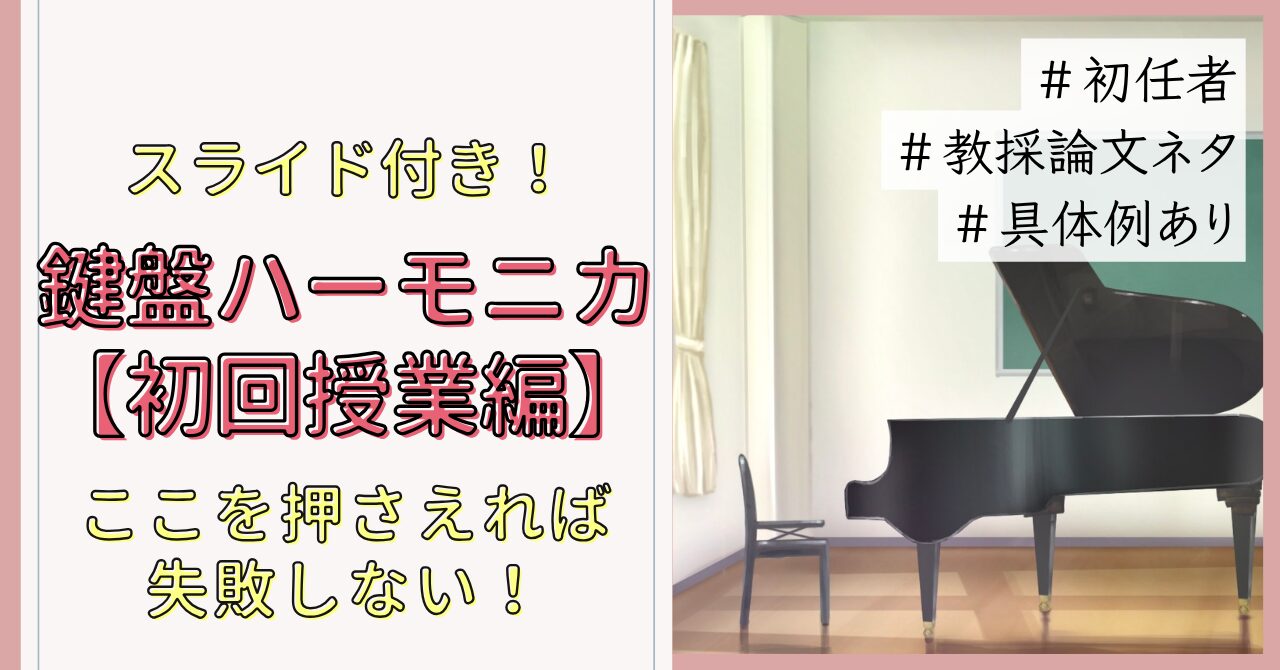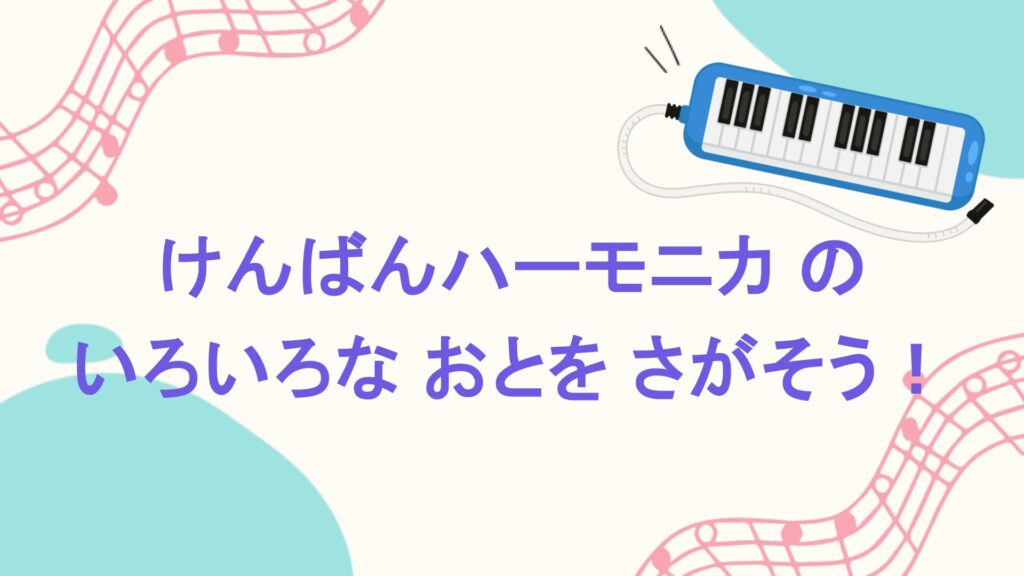こんにちは!元音楽の先生、みきちです☺
今回のテーマは「鍵盤ハーモニカの初回授業」について!
最初の授業は今後の学習に影響するのでとっても重要!と分かっているからこそ、こんなお悩みをお持ちではないでしょうか。
💭何をどこまで教えたらいいの?
💭初回授業で押さえておくべきポイントが知りたい!
とりあえずここを押さえておけば大丈夫!という、最初に指導したいことをまとめました!
3回の授業に分けましたので、今回は、第3回までの大まかな流れと、鍵盤ハーモニカの授業第1回の指導ポイントをお伝えしますね。
そのまま使えるスライドも用意したのでご活用ください✨
💡この記事で分かること💡
☑ 楽しくて、系統的な初回授業~第3回までの流れ
☑ 準備・片付け・音の出し方などの指導ポイント
☑ 初めての児童も経験者も鍵盤ハーモニカに親しめる活動アイデア
授業の流れ(全3時)
子どもたちが楽器への興味を持ち、基本的な扱い方を楽しく学べる「鍵盤ハーモニカの導入」という位置づけです。
✨授業後の理想の児童の姿
・鍵盤ハーモニカに親しみを持ち、今後の授業を楽しみにしている
・楽器を大切に扱う気持ちが持てる
⌛時数
全3時(本記事は第1時)
🎹道具
・鍵盤ハーモニカ(児童用、教師用)
📖共通事項
音色
初回~第3回の大まかな流れ
鍵盤ハーモニカは教えたいことが山盛り!
でも、一気にあれもこれもでは児童もパンクしてしまいます。
こんな流れで指導できると無理なく、無駄なく、系統的に学習できるはずです。一例として参考にされてください。😌
| 主な新出事項 | 活動内容 | |
|---|---|---|
| 第1回 | ・準備・片付けの仕方 ・楽器の扱い方 | ・模範演奏を聴く ・音の鳴る仕組みを触って理解する ・準備・片付けの仕方を知る ・高い音、低い音、長い音、短い音、 クラクションの音で遊ぶ |
| 第2回 | ・唄口(くわえるところ)の持ち方 ・指番号 ・「ド」の位置 | ・唄口の持ち方、指番号、「ド」の位置を知る ・「ド」でリズム模倣ゲーム ・「やさしいひつじ」を歌う |
| 第3回 | ・右手の手の形 ・タンギング(できなくてもOK) | ・右手の形を覚える ・タンギングについて知る ・「ド、レ、ミ」でリズム模倣ゲーム ・「やさしいひつじ」を演奏する |
第1時:鍵盤ハーモニカと なかよくなろう
❁めあて
けんばんハーモニカと なかよくなろう
❁評価の観点(例)
音楽活動を楽しみながら、主体的・協働的に器楽の学習活動に取り組もうとしている。(態)
第1時の流れ
- 模範演奏を聴く(教師の範奏またはYouTube等で視聴)
- 楽器を使う時のお約束を確認する
- 持ち物の確認
- 準備の仕方を知る
- 色々な音を出して遊ぶ(無料スライドあり!)
- 片付けの仕方を知る
- 振り返り
①鍵盤ハーモニカの音を聴こう

今日から鍵盤ハーモニカの学習が始まります!
どんな音がするかな?
まずは、教師が鍵盤ハーモニカを演奏してみせましょう。
- さんぽ
- ミッキーマウスマーチ
- きらきら星(できたら変奏曲風にかっこよくできるといいですね🌠)
などなど、子ども達が知っている曲を和音を入れながらかっこよく演奏してもいいですし、
- こいぬのマーチ
のように、1年生が終わるころにはこんな演奏ができるようになるよ!というのを伝えても良いでしょう。
演奏が得意でなければ、鍵盤ハーモニカのプロの演奏動画などを見せてももちろんOK。
子どもたちが「わぁ、きれいな音!」「かっこいい!」と鍵盤ハーモニカの音色に魅力を感じる最初の出会いが大切です。
②音楽のお約束(ルール)の確認
子ども達は楽器の授業が大好きです。
👦🏻「触りたい!」
👧🏻「音を出してみたい!」
と思う気持ちや、興味自体は悪いものではありません。
寧ろ、そういった気持ちをうまく利用して前向きに取り組めるようにしたいですね。
授業を円滑に進めるために以下の2つを守らせましょう。
- 楽器は大切に扱うこと
- 指示が出てから楽器に触れること(勝手に音を出さない)

守ってほしいお約束が2つあります。
1つ目。楽器は大切にしましょう。
楽器は思ったより簡単に壊れてしまいます。もし壊れたらどうなりますか?音が出なくなってしまうね。自分のものも、他の人のものも、大切に使ってあげようね。

2つ目。楽器は「どうぞ」の合図で音を出します。
みんなが勝手に音を出し始めたらどうなりますか?音がうるさくて嫌だなぁと思う人もいるし、先生の声が聞こえなくなってしまいますね。何かあった時に聞こえなかったら大変です。
楽器の時のお約束。覚えたかな?
最初にしっかりと約束することが、今後の授業をスムーズに進めるための土台になります。
③持ち物・各部の呼び方を確認する
鍵盤ハーモニカは保護者の方にお願いして事前に中身を準備・確認してもらいましょう。
ケースの中に必要なものは以下の4つです。
- 鍵盤ハーモニカ本体
- ホース(卓上用唄口)
- 唄口(立奏用唄口)
- ガーゼ(柔らかい布)
部品の名前について私は上記のように呼んでいましたが、子ども達と意思疎通が図れればそんなにこだわらなくても大丈夫です。
(メーカーさんにもよりますが、「ホース」→「卓上用唄口」 「唄口」→「立奏用唄口」 がメーカーさんの呼び名のようです)
学校では持ち物の確認として、指差し確認させましょう。👆🏻
- ケースを開ける
- 順番に指をさしながら道具を確認する。
- 確認出来たら楽器はそのまま、手はお膝。
④どうして音が出るのかな?~音の鳴る仕組み~
前述の通り、子ども達は演奏したくてたまらないので(笑)、欲求を満たしてあげながら学習を進めましょう。

(鍵盤を見せながら)ここの名前、『鍵盤』と言います。
みんなで鍵盤だけ優しく押してみようか!どうぞ。
あれ?鍵盤を押しただけじゃ音が出ないね。どうやったら音が鳴るのかな?

ホース!ホースを使うんだよ!

そう。このホースは息のトンネルなの。ここを通って本体に風がきます。
よく見ててね。鍵盤を押して、息を入れると…音が出たね!
鍵盤を押すと中の弁が開いて、そこに息が通ることでリードが震えて音が出る、という仕組みです。
これをそのまま伝える必要はありませんが、
- 鍵盤を押すだけでは音は鳴らない。
- 息だけでも鳴らない。
- 押したところだけ、息が通って鳴る。
この3点を端的に伝えましょう。
💡POINT💡
ホースも大切に扱ってほしいので、
「このホース、もし穴が開いたらどうなる?穴から息が逃げてしまって、音が上手く出なくなっちゃうの。だからホースも大切にね。」のように伝えましょう。
これでホース振り回し隊を未然に防げるはずです。😂
⑤準備の仕方を覚えよう!

さあ!いよいよ鍵盤ハーモニカを吹く準備をするよ!先生が「鍵盤準備!」って言ったら、こうやって準備します。今日は一緒にやってみよう!
- ケースを開ける。
- ホースを取り出す。
- ホースを鍵盤ハーモニカ本体にしっかりと取り付ける。
💡手前に回しながら押し込むと外れにくい! - 唄口をホースの根元やケースの取っ手部分などに通して固定する。
💡メーカーによって仕様が異なるので一人一人確認してあげましょう。
一連の流れを、ゆっくりと、子どもたちに見せながら説明します。
その後、「鍵盤準備!」の合図で、子どもたちにも実際に準備させてみましょう。
⑥色んな音を探して遊ぼう!
実際に音を出しながら鍵盤ハーモニカの様々な音に触れさせてあげましょう。スライドも作ったので必要な方はご活用ください🎹
▶▷▶
【そのまま使える!「けんばんハーモニカの いろいろな おとを さがそう」スライド】
▶▷▶
※編集方法:ファイル→コピーを作成
※Googleスライドに変更:ファイル→Googleスライドとして保存
- 一番高い音はどこ?
- 一番低い音はどこ?
- 短い音の出し方は?
- 長い音の出し方は?
- グリッサンド(息を入れながら下から上、上から下に指を滑らせる)で遊ぶ
時間があれば、以下のような活動もアリです!
- 黒い鍵盤の数を数える
- 黒い鍵盤の「2つのお山」を同時に鳴らすと何の音?
- 「ド」の位置を覚えよう

鍵盤ハーモニカを演奏して、色んな音を見つけて遊んでみよう!
先生が「どうぞ」と言ったら10秒だけ音を出していいです。
問題に合う音を探してね。
じゃあ第一問!一番高い音はどこかな?10秒で探してみよう。どうぞ!
💡POINT💡
私は音を止めてほしい時の合図として「ドミソ」を3回鳴らしていました。
他の先生方は以下のような方法で合図を作っていました。
- トライアングルでトレモロ(チリリリリリ…)を演奏する
- お辞儀の音楽(ミソド、レソシ、ミソド)
- 電子黒板でタイマーをかける
今の私なら、「猫ふんじゃった」の最後の音(ドッソソラ♭ーソ、 シ、ド♪)を使って、最後の「ちゃんちゃん♪」を児童に手拍子させるかな…と思います🐈笑
このようなルールを普段から習慣づけると、話を聞いてほしい時にパっと集中できることができます。
⑦片付けまでが楽器の時間 ~楽器の片付け方~

色んな音を見つけられたね!鍵盤ハーモニカさんは今日一日頑張ってくれたので、きちんと綺麗にしてから片付けしましょう。
「鍵盤片付け!」って言ったら、こうするよ。今日は一緒にやろうね。
- ガーゼ(またはハンカチなど柔らかい布)を準備する。
- 片手で本体を持ち、もう片方の手でホースの黒い部分(本体との接続部分)を回しながらホースを外す。
- ガーゼを手のひらの上に広げ、ホースの黒い部分(唄口が付いている方)を下にして、ガーゼにトントントンと優しく叩きつけるようにして、中の水滴を出す。
- ホースをケースにしまう。
- ガーゼを膝の上に置く。
- 鍵盤本体の、ホースを付けていた穴が下になるように持ち、ガーゼの上で同様にトントントンと優しく叩き、水滴を出す。
- 本体をケースにしまい、ケースの蓋をきちんと閉じる。
準備と同様に、一つ一つの手順を見せ、できているか確認しながら説明します。
片付けまでが楽器の時間!低学年のうちにぜひ習慣化したいですね🎶
⑧めあてを振り返る
- 準備や片付けの仕方が分かったよ という人!
- 鍵盤ハーモニカがどうして音が鳴るのか分かったよ という人!
- 鍵盤ハーモニカの色んな音を楽しむことができたよ という人!
などなど、挙手でめあての達成度を確認しましょう。🙋🏻♀️
まとめ
鍵盤ハーモニカの導入はとっても大事!
子ども達は音を出してみたくてワクワクしていることでしょう。
苦手意識を持たせてしまうと今後のやる気に関わるので、先生自身が今後の流れを意識して教えること・習得してほしいことを整理する必要があります。
「できる!」「楽しい!」といった実感を持たせて楽器への興味を引き出す一例として、ご提案させていただきました!
児童の実態に合わせてご活用くださいね。
音楽分からん!アイディアがない!相談できる人がいない!時間もない!
ほんの少しでも、そんな先生方のお力になれますように🎹✨